Aさんには10歳近く年下の内縁の妻がいます。子供はおらず、両親と兄が他界しているため相続人は甥と姪のみです。
今回は内縁の妻亡き後に思い通りに分配したいケースとして家族信託が利用されている具体的な事例をご紹介いたします。
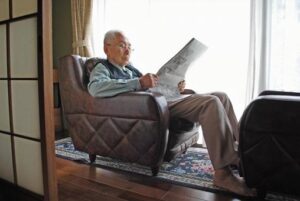
家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。
現在の状況
Aさんは72歳で川口市の飯塚で暮らしています。Aさんには65歳の内縁の妻がいて子供はいません。
Aさんにはお兄さんがいますがすでに亡くなっています。そのお兄さんには子供がいます。従ってAさんの法定相続人はお兄さんの子供である甥と姪のみです。

Aさんは長年連れ添った内縁の妻Bには不自由をかけたくないので、遺産は全て内縁の妻に渡したいと考えています。(内縁の妻は法定相続人ではありません。)しかしBには法定相続人が一切いないので内縁の妻が亡くなった後には、不動産等を売却した後、一部のお金を甥Cに渡して、残りは障害を持った子供たちの施設に寄付をしたいと考えています。このような場合どのように相続対策していくのがいいのでしょうか?
家族信託の計画
・委託者 : A
・受託者 : 甥っ子C
・受益者 : A、内縁の妻B
・信託財産 : 自宅と現金
・信託期間 : AおよびBの死亡まで
・残余財産の帰属先 : 甥Cと障害福祉施設
家族信託のポイント
遺言や信託による資産の継承先の指定がない場合、内縁の妻Bは相続権が一切ないためAさんの甥っ子や姪っ子に全て財産が相続されます。そこで信託契約の中で遺言と同じような機能を持たせ、第二受益者として内縁の妻Bを指定することで内縁の妻Bが生きている間の生活保障を実現することが可能です。ちなみに甥や姪には遺留分がないため確実に財産を引き継がせることができます。
Aさんや内縁の妻Bの老後の資金繰りが難航して入所資金捻出のために自宅を処分する場合や、Aさんと内縁の妻Bが亡くなって信託契約が終了した後でも、福祉施設に寄付をしやすいように甥Cは自分の判断で自宅不動産を売却できるようになっています。またCの長期にわたる世話の負担の報酬として信託報酬を設定します。司法書士Zに信託監督人として、甥Cの業務を監督したり、甥Cの相談に乗ったり、AさんやBさんの生活状況を確認する役割などを担ってもらいます。

